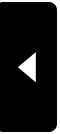2012年03月05日10:33
坐禅入門⑧ー禅堂の作法と坐禅の仕方(解説編)≫
カテゴリー │坐禅入門
仲間でサッカーを楽しむには、サッカーのマナーやルールーを知って守るように、
禅堂にも基本的な作法やルール(決まり)があります。
何人かの仲間が集まって坐禅する場合はもちろん、家で独りで坐る時でも、
そういう作法や決まりにしたがって坐禅をすることで、
気持ちがシャンとして禅定・三昧に入りやすくなります。
白隠禅師が称歎する「摩訶衍(マカエン)の禅定」は、
大乗の真理の道に志す仲間が、共に力を合わせてする禅定ですから、
家で独りで坐っている時でも、日本中いや世界中の「いまここ禅道場」の仲間と共に坐っているという気持ちが大切です。
坐禅や祈りの精神の波動は、時空を超えて共振すると感じています。
【禅堂の基本作法】
①禅堂では沈黙を守ります。皆が自己に沈潜し禅定に入るためです。
ですから、坐禅の初めと終わりなど、柝(たく、拍子木)や引磬(いんきん、手持ちの鐘)などの鳴らしもので知らせます。
②叉手(しゃしゅ)
叉とは「さしはさむ」ことで、
左手を外側にして左右の手を重ねてさしはさみ、胸の前あたりに保ちます。
禅定の落ちついた心を保持している姿です。
③合掌(がっしょう)
人や物など、相手を敬う気持ちや感謝の気持ちの表現です。
10本の指はまっすぐに伸ばし指と指が離れないように合わせて、自然に胸の前あたりに保持します。
④合掌低頭(がっしょうていとう)
合掌のまま少し頭を下げます。
⑤叉手出班・合掌帰班(しゃしゅしゅっぱん・がっしょうきはん)
叉手で出て合掌で帰ります。
自分の立ち位置・基点を班と言います。禅堂の修行僧・雲水にとっては禅堂内のタタミ一畳が自分個人の生活の場であり基点・班となります。
ですから、自分の坐禅布団のある所に行くのは帰ることになり、坐禅布団から離れるのは出ることになります。
出る時は叉手、帰る時は合掌します。坐禅布団の前と禅堂の入り口前では合掌低頭します。
⑥左進右退(さしんうたい)
前に歩みはじめるのは左足から、後ろに退くのは右足から。
⑦その他
タタミの縁はふまないようにします。
斜めには進まず、角かどを直角に進みます。
以上、初めての方は「ややこしくて、めんどうだ」と感じられるでしょうが、茶道の作法がそうであるように、慣れてくればごく自然にできるようになります。
【身心学道】
禅は「身心学道(しんしんがくどう)」と言うように、身と心を一つにして真実の生き方を学ぶ道です。
身体の形(フォーム)がそのまま心となるということで、あれこれの思いや理屈よりも、先ず身体の形・威儀から入っていくわけです。
「威儀即仏法(いぎそくぶっぽう)」です。
ですから、南無といい、帰依といい、自分の身も心も投げ出し天地宇宙の大生命と一つになる身をもってする行が大切です。
叉手、合掌、入退堂、坐禅などすべてが身心学道ですから、心をこめ正しく美しく行うようにしましょう。
皆さんは「いまここ禅道場」の同志ですから、家で独り坐禅する時でも、世界中の仲間、生きとし生けるものすべてと共に大道を歩んでいるという天地一杯の心で坐禅してください。
※続けてYouTube動画編を配信します。音声の編集がうまくいかないので、動画にコメントを貼り付けました。
ウイークエンドの「いまここ塾」の坐禅会・接心の前に、家で自習していただくよう続編も配信します。
七日から二泊三日、阿部さんの紹介で比叡山に行ってきます。比叡山学院院長の堀澤祖門師(天台宗大僧正、81歳)のお招きです。まさに勝縁、今からワクワクしています(^▽^)
禅堂にも基本的な作法やルール(決まり)があります。
何人かの仲間が集まって坐禅する場合はもちろん、家で独りで坐る時でも、
そういう作法や決まりにしたがって坐禅をすることで、
気持ちがシャンとして禅定・三昧に入りやすくなります。
白隠禅師が称歎する「摩訶衍(マカエン)の禅定」は、
大乗の真理の道に志す仲間が、共に力を合わせてする禅定ですから、
家で独りで坐っている時でも、日本中いや世界中の「いまここ禅道場」の仲間と共に坐っているという気持ちが大切です。
坐禅や祈りの精神の波動は、時空を超えて共振すると感じています。
【禅堂の基本作法】
①禅堂では沈黙を守ります。皆が自己に沈潜し禅定に入るためです。
ですから、坐禅の初めと終わりなど、柝(たく、拍子木)や引磬(いんきん、手持ちの鐘)などの鳴らしもので知らせます。
②叉手(しゃしゅ)
叉とは「さしはさむ」ことで、
左手を外側にして左右の手を重ねてさしはさみ、胸の前あたりに保ちます。
禅定の落ちついた心を保持している姿です。
③合掌(がっしょう)
人や物など、相手を敬う気持ちや感謝の気持ちの表現です。
10本の指はまっすぐに伸ばし指と指が離れないように合わせて、自然に胸の前あたりに保持します。
④合掌低頭(がっしょうていとう)
合掌のまま少し頭を下げます。
⑤叉手出班・合掌帰班(しゃしゅしゅっぱん・がっしょうきはん)
叉手で出て合掌で帰ります。
自分の立ち位置・基点を班と言います。禅堂の修行僧・雲水にとっては禅堂内のタタミ一畳が自分個人の生活の場であり基点・班となります。
ですから、自分の坐禅布団のある所に行くのは帰ることになり、坐禅布団から離れるのは出ることになります。
出る時は叉手、帰る時は合掌します。坐禅布団の前と禅堂の入り口前では合掌低頭します。
⑥左進右退(さしんうたい)
前に歩みはじめるのは左足から、後ろに退くのは右足から。
⑦その他
タタミの縁はふまないようにします。
斜めには進まず、角かどを直角に進みます。
以上、初めての方は「ややこしくて、めんどうだ」と感じられるでしょうが、茶道の作法がそうであるように、慣れてくればごく自然にできるようになります。
【身心学道】
禅は「身心学道(しんしんがくどう)」と言うように、身と心を一つにして真実の生き方を学ぶ道です。
身体の形(フォーム)がそのまま心となるということで、あれこれの思いや理屈よりも、先ず身体の形・威儀から入っていくわけです。
「威儀即仏法(いぎそくぶっぽう)」です。
ですから、南無といい、帰依といい、自分の身も心も投げ出し天地宇宙の大生命と一つになる身をもってする行が大切です。
叉手、合掌、入退堂、坐禅などすべてが身心学道ですから、心をこめ正しく美しく行うようにしましょう。
皆さんは「いまここ禅道場」の同志ですから、家で独り坐禅する時でも、世界中の仲間、生きとし生けるものすべてと共に大道を歩んでいるという天地一杯の心で坐禅してください。
※続けてYouTube動画編を配信します。音声の編集がうまくいかないので、動画にコメントを貼り付けました。
ウイークエンドの「いまここ塾」の坐禅会・接心の前に、家で自習していただくよう続編も配信します。
七日から二泊三日、阿部さんの紹介で比叡山に行ってきます。比叡山学院院長の堀澤祖門師(天台宗大僧正、81歳)のお招きです。まさに勝縁、今からワクワクしています(^▽^)
この記事へのコメント
ご指導ありがとうございます。こういう雛形があるとやりやすいですね。
「いまここ禅道場」の同志!仲間がいると思うと心強いですね
比叡山レポート楽しみにしています。宗派を超えて素晴らしいですね。
「いまここ禅道場」の同志!仲間がいると思うと心強いですね
比叡山レポート楽しみにしています。宗派を超えて素晴らしいですね。
Posted by たこ at 2012年03月07日 22:41
いつもブログ更新ありがとうございます。
比叡山、どうぞ楽しんでいらしてくださいませ。
比叡山、どうぞ楽しんでいらしてくださいませ。
Posted by Pika at 2012年03月08日 00:20
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。